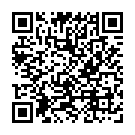| 検査項目 | 検査の意味 | |
|---|---|---|
| 腹 囲 | メタボリックシンドロームの判断基準のひとつです。内臓脂肪の蓄積の目安にします。 | |
| BMI | 肥満度の指標 BMI =体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)で求められます。BMI 22前後が最も病気になりにくいといわれています。 | |
| 血圧 | 収縮期血圧は、心臓から血液が送り出されるときの血圧、収縮期血圧は血液が心臓に戻ったときの血圧です。高血圧が長く続くと血管が早く老化して動脈硬化を起こしやすくなり、脳卒中や心臓病などの危険が高まります。 | |
| 肝機能 | AST(GOT) | 肝臓に含まれる酵素です。数値が高い場合は、肝臓や心筋、骨格筋などの臓器の異常や障害が疑われます。 |
| ALT(GPT) | ほとんどは、肝細胞に含まれ、この数値が高いとウイルス性肝炎、アルコール性肝障害、脂肪肝などの肝臓障害が疑われます。 | |
| γ-GT(γ-GTP) | 肝臓・胆道に障害があると数値が高くなり、特にアルコール性肝障害の指標になります。 | |
| 血中脂質 | 中性脂肪 | 主にエネルギーとして利用され、余りは脂肪として体内に蓄積されます。食べ過ぎ・飲みすぎ・肥満によって数値が高くなり、動脈硬化や肥満の原因になります。 |
| 総コレステロール | コレステロールは身体の中で重要な役割を果たしています。新しい細胞を作る際の細胞膜構成成分としても欠かせません。しかし、高すぎると動脈硬化を引き起こします。高すぎても低すぎてもさまざまな支障が出てきます。 | |
| HDLコレステロール | 善玉コレステロールと呼ばれます。動脈硬化の原因になりやすいLDLコレステロール(悪玉コレステロール)を取り除く働きがあります。 | |
| LDLコレステロール | 悪玉コレステロールと呼ばれます。血管の内側に付着し、動脈硬化を進行させます。さらに血管をふさいで血流を悪くし、心筋梗塞や脳梗塞を引き起こします | |
| その他血液検査 | アルブミン | 肝臓でつくられ、肝臓そのものに障害があると減少します。慢性疾患や低栄養状態で低くなります。 |
| ALP | 主に肝臓や骨で生成される分解酵素です。 | |
| 総蛋白 | 血液中の蛋白量。肝臓、腎臓の異常で数値が変動します。 | |
| 総ビリルビン | 黄色い色素で、数値が上昇すると皮膚や眼球が黄色くなります。 | |
| 腎機能 | 血清クレアチニン | クレアチニンは蛋白質の老廃物の一種です。血液中に含まれる数値が高い場合は、腎機能の低下が疑われます。 |
| eGFR | 腎臓の糸球体が1分間にどのくらいの量の血液をろ過し、尿をつくれるかを示す値でクレアチニン値をもとに算出しています。おおよそ腎機能のパーセンテージに対応しています。 | |
| 尿酸 | 腎機能障害や痛風のときなどに上昇します。 | |
| 糖代謝 | 血 糖 値 | 血液中のブドウ糖のことで、すい臓から出るインスリンというホルモンが不足したり、作用が足りないと血糖値が高いままになります。糖尿病の診断に欠かせません。空腹時血糖は絶食10時間以上、随時血糖は食後3.5時間以上絶食10時間未満に採血が実施されたものとされています。 |
| ヘモグロビンA1c | 血液中のヘモグロビンがブドウ糖と結合したもので、過去1〜2か月の平均的な血糖値がわかります。 | |
| 尿 | 尿糖 | 血液中に含まれるブドウ糖が尿中に排泄されたもので、糖尿病の進行状態を判断することができます。 |
| 尿蛋白 | 血液中に含まれる蛋白が尿中に出たもので、健康な人でも一時的に出ることもあります。持続して陽性のときは、腎炎・ネフローゼなどの腎臓の疾患が疑われます。 | |
| 尿潜血 | 腎臓・尿管・膀胱などの尿路に炎症・結石・腫瘍があると尿に血液が混じります。目で見えない少量の出血も検出します。 | |
| 尿比重 | 尿比重とは、尿の中の水分と、水分以外の物質の割合を算出したものです。尿には余分な水分のほかに、体内活動の結果として含まれる老廃物(尿素や窒素、ナトリウム、クロールなど)が含まれています。そのため、尿の比重は水よりもやや高く、健康時には1.010〜1.030といった範囲で変動しています。 | |
| 尿沈査 | 尿の中に出てきた細胞成分や細菌などを顕微鏡で調べる検査。細胞成分には、赤血球、白血球、尿細管・膀胱から脱落したもの)、それらがつまった円柱などがあり、これらがどれだけみられるかによって判定します。 | |
| PH | 尿pHのpHとは水素イオン濃度の略称で、酸性度とも呼ばれます。健康な人の体では通常尿は弱酸性に維持されるように調整されます。一日の間でも尿pHは変化し、特に睡眠時には尿は酸性に傾きます。 | |
| 血液一般 | 赤血球 | 血液1㎣に含まれる赤血球の数です。少なければ貧血が疑われますが、貧血の診断は血液関連検査の結果と併せて総合的に行われます。 |
| 白血球 | 感染や炎症疾患があるときなどに増加します。血液の病気では減ることがあります。 | |
| ヘマトクリット | 血液全体に占める赤血球の容積の割合を示した値で、基準値を下回る場合、貧血が疑われます。 | |
| ヘモグロビン | 赤血球に含まれるヘムたんぱく質で、体内の酵素を運ぶ働きをしています。血液中の血色素濃度を調べることによって鉄欠乏性貧血などの有無がわかります。 | |
| 血小板 | 減少すると出血しやすく血も止まりにくくなります。 | |
| MCV | ヘマトクリット値 / 赤血球数 × 10 ヘマトクリット値、つまり容積を 赤血球数で割ったもので、赤血球の1個あたりの容積の平均値です。赤血球の大きさの判断に役立つ指数です。 | |
| MCH | 血色素量 / 赤血球数 × 10 一定量の中の血色素量を、赤血球数で割ったもので、赤血球の1個あたりのヘモグロビン量の平均値です。 | |
| MCHC | (血色素量 / ヘマトクリット値) × 100 個々の赤血球の容積に対する血色素量の比を%で表したもので血色素濃度の高低、すなわち低色素性、高色素性の程度を示します。 測定した3つの項目(MCV、MCH、MCHC)の検査結果と、この3つの計算式によって血液中の赤血球の状態や機能・能力を推測します。 | |
| 循環器 | 心電図 | 心臓が収縮するときに発生する微弱な電流の変化を波形として記録し、心臓の働きを調べる検査です。 |
| 心拍数 | 一定の時間内に心臓が拍動する回数。通常は1分間の拍動の数。 | |
| 胸部 | 胸部X線 | 胸部をX線で撮影し、異常がないかを検査します。 |
| 肺機能 | 肺機能検査 | 肺にどのくらいの空気が入るかや、空気を出し入れする換気機能のレベルを検査します。 |
| 腹部 | 腹部エコー | 腹部に超音波を発信し、その反射波(エコー)を利用して画像化・解析する検査です。主に肝臓、胆のう、すい臓、ひ臓、腎臓などの臓器に異常がないかを検査します。 |
| 大腸 | 便潜血 (2回法) |
消化管のどこかに出血があると便に血が混じります。少量ですと肉眼ではほとんどわかりません。便の中の血液成分を調べることによって、その有無がわかります。 |
| 胃部 | 内視鏡 (経口・経鼻) |
内視鏡を使って、咽頭の一部、食道・胃・十二指腸を内側から直接的に観察する検査です。検査を行う際には、喉の麻酔をした後に内視鏡を口(あるいは経鼻内視鏡では鼻)から入れて観察をします。色素を撒いたり、特殊な光による観察を追加したりすること、さらには病変から一部組織を取る(生検)こともあります。 |
| 眼科 | 眼底検査 | 眼底カメラで網膜の写真を撮ります。高血圧や糖尿病による影響や動脈硬化の有無や程度を知ることができます。 |
| 眼圧検査 | 眼球に空気を当て眼球内圧を測定します。緑内障の場合は上昇します。 | |
| 感染・炎症 | B型肝炎 | B型肝炎ウイルスに感染しているかを調べる検査です。 |
| 梅毒検査 | 梅毒に感染しているかを調べる検査です。 | |
| CRP | 炎症や組織の損傷があると上昇します。 | |
|
病気や検査のお話し |
全身性エリテマトーデスの腎病変 |